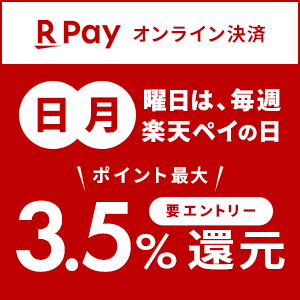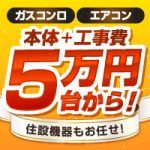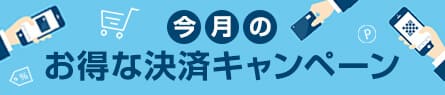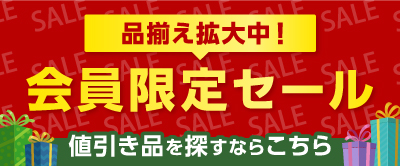夏などジメジメした季節は汗をかきやすく、布団にも湿気がこもりがちです。
放置しておくとダニやカビの原因となるため、なるべくなら外干ししたいですが、天候やライフスタイルの関係で難しい方も多いのではないでしょうか。
そこで役に立つのが、布団乾燥機です。
ダニ退治はもちろんのこと、消臭対策から衣類乾燥まで、1台で何役もこなす便利な家電です。
この記事では、布団乾燥機の使い方のコツや選び方の注意点などについてまとめました。
おすすめランキングも紹介しますので、購入や買い替え時の参考にしてください。
ダニや湿気対策に最適な布団乾燥機とは?

布団乾燥機とはダニや湿気対策に効果的な家電のことで、大きく分けて次の3種類あります。
- マット式
- ノズル式
- スティック型
マット式は、敷き布団と掛け布団の間に乾燥用のマットをセットし、スイッチを入れるとホースから温風が出て布団を温める仕組みです。
ノズル式は、敷き布団と掛け布団の間にホースを差し込み、スイッチを入れてホースから温風を送り込み、布団全体を温めます。
スティック型は、敷き布団と掛け布団の間に本体を設置し、スイッチを入れると温風が広がって乾燥させる仕組みです。
それぞれのメリットとデメリットの比較は、以下の表をご覧ください。
| 布団乾燥機のタイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| マット式 |
|
|
| ノズル式 |
|
|
| スティック型 |
|
|
このように、タイプによってメリット・デメリットが異なります。
収納スペースや使用頻度なども考慮し、家庭に合わせたものを選ぶといいでしょう。
布団乾燥機 はこちら
温風・送風による効果的な除湿方法
布団乾燥機の多くは温風・送風などの様々な機能を有しており、用途に応じて使い分けることで、より効果的な除湿対策ができます。
ダニ退治には、50度以上の温風が出るモデルがおすすめです。
ダニは乾燥に弱いため、布団内の温度を60~70度まで高めることで、ダニが生息しにくくなります。
ただし、ダニは温風から逃れようとして布団の裏側へ潜る場合がありますので、心配なら布団の裏側も乾燥させるといいでしょう。
なお、退治後の死骸をそのままにしておくと、アレルギーやほかのダニを呼び寄せてしまう原因となります。
布団乾燥機の使用後は布団クリーナーや掃除機をかけて、ダニの死骸をきれいに吸い取っておきましょう。
季節家電として活躍する理由
製品やメーカーにもよりますが、布団乾燥機は季節家電としても活躍します。
梅雨や夏場のように湿気の多い時期は汗をかきやすく、室内の温度や湿度も上がるため、布団が湿ってカビの原因になりやすいです。
定期的に布団を外干しできれば理想的ですが、天候や時間の関係で難しい場合もあります。
そのようなときに布団乾燥機があると、いつでも外干ししたような布団で眠れて快適です。
また、花粉症などの理由から、花粉が飛散する時期は外干ししたくてもできずにお悩みの方もいるでしょう。
こうした場合にも、布団乾燥機があれば、しっかりと布団を乾燥させられます。
黄砂やPM2.5、排気ガスなどが気になって外干しできないという方にもおすすめです。
布団乾燥機の購入前に知っておきたい注意点と使い方のコツ

一口に布団乾燥機といっても、搭載されている機能や性能はメーカーや製品によって異なります。
ここでは、布団乾燥機の購入前に知っておきたい注意点と使い方のコツについて解説しますので、参考にしてください。
電気代や消費電力を抑える省エネ使用法
布団乾燥機を毎日使用し続けていると、その分電気代がかかります。
特に家族全員分の布団を乾燥させるとなると、より電気代がかさんでしまうでしょう。
消費電力を抑えるには、取扱説明書をよく読み、メーカーが推奨する使用方法で正しく操作することが大切です。
また、布団に隙間ができていると、せっかく温風を送り込んでも逃げていってしまいますので、隙間なくセッティングしましょう。
本体内部のフィルターにホコリやゴミがたまると、本来の性能を発揮できずに乾燥効果が下がり、無駄に電力を消費してしまいます。
定期的にフィルターを掃除して清潔を保つことで性能がキープされ、電気代の節約にもつながるでしょう。
静音設計やタイマー機能が便利なシーン
布団乾燥機は本体内部にファンやモーターが搭載されており、使用中に動作音が発生します。
そのため、お子さんや音に敏感な方であれば、「うるさい」と感じてしまうかもしれません。
静音設計のモデルであれば、動作中の音が気になりにくいでしょう。
また、タイマー機能が搭載されていれば、布団を数分間だけ温めたいというときなどに便利です。
床に防音マットを敷くのもいいでしょう。
特に集合住宅にお住まいの場合は騒音が問題になりやすいため、こうした対策をしておくことで、トラブルを未然に防げます。
また、夜間や早朝に使用しない気遣いも大切です。
布団乾燥機選びで失敗しないための注意点

次に、布団乾燥機選びで失敗しないための注意点について解説します。
サイズと収納性を確認しよう
布団乾燥機を毎日ではなく、必要なときにだけ使いたいという場合に困るのが、置き場所です。
とりあえず購入したものの、空いている隙間に無理に押し込んだり、物置部屋の隅にいつの間にか追いやっていたりする方も多いのではないでしょうか。
このような状態だとすぐに取り出せないばかりか、乱雑に扱うことで故障などの原因にもなってしまいます。
そこで、まず確認しておきたいのが、布団乾燥機のサイズと収納性です。
使いたいときにすぐに取り出せて簡単にしまえるスペースがあるか確認した上で、サイズ感に合う機種を選びましょう。
近年はコンパクト設計の機種も増えていますので、こうした製品を選ぶと場所を取らずに収納できます。
また、デザイン性の高い製品であれば、出しっぱなしにして「あえて見せる」収納もおすすめです。
機能の優先順位を決めよう
次に考えたいのが、機能の優先順位です。
ダニ退治がメインなのか、衣類乾燥にも使いたいのかといった優先順位をもとに、必要な機能が付いた製品を選びましょう。
布団乾燥機に搭載されている主な機能は、以下の通りです。
<ダニ退治>
50度以上の温風を一定時間送り込むことで、ダニを退治します。
機種や布団の大きさにもよりますが、効果が期待できるまでには数十分以上の時間がかかるケースが多いです。
また、徹底的にダニを退治したい場合は、表と裏の複数回に分けて稼働させる必要があります。
布団乾燥機 はこちら
<消臭・脱臭>
イオンを放出し、布団や枕を消臭・脱臭する機能です。
衣類や室内の消臭ができる製品や別売のデオドラント剤をセットして消臭する製品もあります。
消臭機能付き はこちら
<衣類乾燥>
室内干しした洗濯物に温風を当て、乾燥させる機能です。
製品によっては、専用の衣類カバーで対象となる洗濯物を包み込み、その中に温風を送り込む機種もあります。
衣類乾燥機能付き はこちら
<靴乾燥>
ノズルや専用アタッチメントを靴の中に差し入れ、温風を送り込んで乾燥させます。
雨や雪、水遊びなどで濡れた靴を乾かしたいときに役立つ便利な機能です。
なお、熱に弱い素材でつくられた靴には、基本的に使用できません。
ただし、送風であれば使える場合がありますので、取扱説明書を確認しましょう。
靴乾燥機能付き はこちら
<布団温め>
温風を送り込んで布団を温める機能です。
特に冬は布団の中まで冷えており、寒くてなかなか眠れないという方も多いでしょう。
そのようなときに布団温めモードを使うと、いつでも干したてのようなフカフカの温かい布団で眠れます。
<クールダウン>
温めた布団をクールダウンする機能で、機種によっては、夏モードや送風モードとも呼ばれます。
ダニ対策モードで温めた後の布団には熱がこもっており、暑い時期だととても眠れたものではありません。
こうした状況で役に立つのがクールダウン機能で、布団を冷ますことで夏の夜も快適に眠れます。
<アロマ>
専用カートリッジなどを取り付け、布団に香りをつける機能です。
香りが持つリラックス効果により、快適な眠りをサポートします。
手持ちのアロマオイルをそのまま使える機種もあれば、用意された香りの中から選ぶタイプもあります。
電気代や運転音も要チェック
電気代や運転音も要チェックです。
乾燥が終わったらすぐに電源を切ったり、時間を決めて停止させたりするなど、必要以上に電気代がかからないよう工夫しましょう。
一般的にダニ退治モードは通常モードよりも電気代がかかりやすいため、ダニ退治モードの使用頻度を抑えるのも効果的です。
機種によっては、節電モードや送風モードなど、消費電力の少ないモードが搭載されたものもあります。
また、省エネに対応したモデルを購入するのもおすすめです。
可能であれば、契約中の電力プランの見直しも検討してみましょう。
運転音については、一概にはいえませんが、一般的にワット数が大きいとパワーも大きいため、運転音が気になりやすい傾向にあります。
静音モードが搭載されたモデルなら、音に敏感な方も使いやすいでしょう。
実際に店舗に行き、運転中の音を確認した上で購入するのも一手です。
布団乾燥機おすすめランキング

ここからは、おすすめの布団乾燥機をピックアップして紹介します。
新規購入や買い替えを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
売れ筋商品の一覧
まとめ
布団乾燥機は、天候や時間帯に関係なくいつでも布団を乾燥させられ、快適な睡眠につながります。
ダニ退治だけではなく、消臭、衣類乾燥など、1台で様々な役割を果たす便利な家電です。
日常使いはもちろんのこと、季節に応じて湿気対策や花粉症対策としても役立ちます。
サイズ感や搭載されている機能、電気代や運転音といった項目を参考に、家庭に合わせた商品を選びましょう。