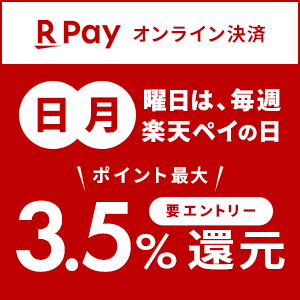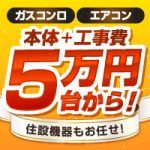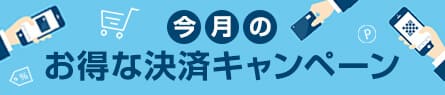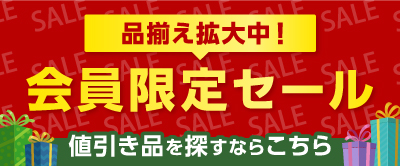ホットカーペット(電気カーペット)は寒い季節に活躍する便利な暖房器具ですが、電気代がどのくらいかかっているのか気になる方もいるでしょう。
ホットカーペットの電気代がわかれば、有効な節約方法を考えることも可能です。
今回は、ホットカーペットの電気代の目安を解説します。
エアコンやこたつなど他の暖房器具と比較して電気代が高いかどうかを説明するとともに、具体的な節約方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ホットカーペットの電気代の目安

ホットカーペットの電気代を知るために、時間・使用期間別の電気代を算出し、他の暖房器具と比較してみましょう。
時間別・期間別のホットカーペットの電気代目安
ホットカーペットの電気代の目安は、1時間あたり6.2〜21.7円です。
電化製品の電気代の計算式である「消費電力量(kWh)×電力量料金(円/kWh)」に当てはめると、電気代の目安を算出できます。
ホットカーペットのサイズ別の消費電力を見ると、1畳用は200W、2畳用は500W、3畳用は700W程度が一般的です。
「W」は1時間(h)をかけて1,000で割ることで、「kWh」に直して計算に使いましょう。
電力量料金は家庭によって異なりますが、今回は公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が算出した目安単価である31円/kWhを使います。
上記の式に当てはめて計算すると、ホットカーペット使用時の電気代1時間あたりの目安は1畳で6.2円、2畳で15.5円、3畳で21.7円です。
1日8時間使った場合の電気代は1畳で49.6円、2畳で124円、3畳で173.6円となります。
また、1ヶ月(30日)間使用すると電気代は1畳で1,488円、2畳で3,720円、3畳で5,208円です。
ホットカーペットと他の暖房器具の電気代を比較
上記で算出した電気代を他の暖房器具と比較して、ホットカーペットの電気代が高いかどうかを判断しましょう。
■エアコン■
エアコン暖房の1時間あたりの電気代は10〜25円が目安なので、ホットカーペットのほうがやや安いとわかります。
ただし、ホットカーペットとエアコンは用途が異なる暖房器具です。
ホットカーペットは床を暖かくするためのもので、エアコンは室内全体を暖かくできます。
適切に使い分けることで、快適な空間を保てるでしょう。
エアコン はこちら
■こたつ■
こたつの電気代は1時間あたり約2〜6円なので、ホットカーペットよりも電気代を抑えられます。
こたつは全身を包んで暖かさを保てる一方で、サイズが大きいためかさばるのがデメリットです。
ホットカーペットは電気代が高めですが、使う場所を手軽に変えられるため、どちらを使うべきかよく考えましょう。
こたつ はこちら
■セラミックファンヒーター■
セラミックファンヒーターの1時間あたりの電気代は、17〜37円が目安です。
ホットカーペットよりもやや高いですが、セラミックファンヒーターは室内を効率的に暖められます。
敷いている場所を暖かくするホットカーペットとは目的が異なる器具なので、適切に使い分けるのがおすすめです。
セラミックファンヒーター はこちら
■ハロゲンヒーター(電気ストーブ)■
電気ストーブ(ハロゲンヒーター)の電気代は、1時間あたり約12〜24円です。
ホットカーペットよりも電気代は高いものの、室内空間全体を速やかに暖められます。
ホットカーペットと併用することで、寒い季節でも快適性を保てるでしょう
ハロゲンヒーター はこちら
■床暖房■
床暖房の1時間あたりの電気代は、15〜35円程度が目安です。
ホットカーペットよりも広範囲を暖められるからこそ、電気代は高くなりやすいです。
しかし、家が広い場合や家族の人数が多い場合などは、床暖房を使うことで快適性を高められます。
電気代と快適性を考慮し、どちらを導入するか判断してください。
ホットカーペットのメリット・デメリット

ホットカーペットのメリットとデメリットを確認し、使うかどうかを判断しましょう。
ホットカーペットのメリット
ホットカーペットのメリットとして考えられるのは、以下のとおりです
■サイズの選択肢が幅広い■
ホットカーペットは、サイズの選択肢が幅広いのがメリットです。
1畳用や2畳用など、複数のサイズ展開をしている製品も多くあります。
狭い場所で使うなら1畳用、リビングなどの広い場所に置くなら3畳用など、用途に合わせてサイズを選ぶことが可能です。
■カーペットとして日常使いができる■
ホットカーペットは、電源を入れなければ通常のカーペットとして日常使いできます。
1年中使えるため、無駄な買い物をしたくない方も満足できるでしょう。
■手軽に掃除ができる■
ホットカーペットは、手軽に掃除できるのもメリットです。
通常のカーペットと同様に掃除機や粘着式のクリーナーなどを使えば付着したゴミを取り除けます。
また、製品によっては高温で運転してダニ対策ができる機能も搭載されているため、衛生的に使えます。
■たたんで収納できる■
寒い時期のみホットカーペットを使おうと考えている場合、使わない時期はたたんで収納できます。
コンパクトにたためば場所を取らないため、暖房を使わない季節も邪魔になりません。
ホットカーペットのデメリット
ホットカーペットには多数のメリットがある一方、デメリットもあるため必ず確認してください。
■室内全体を暖めることはできない■
ホットカーペットは足元など接している部分のみを暖める暖房器具なので、室内全体を暖めることはできません。
室温を高めたいなら、エアコンや電気ストーブなど他の暖房器具と併用する必要があります。
■電気代が比較的高い■
ホットカーペットは、暖房効果に比べて電気代が比較的高いのがデメリットです。
エアコンや電気ストーブなどはホットカーペットよりも電気代が高いものの、空間全体を効率的に暖められます。
電気代は安くても、接している部分のみを暖めるホットカーペットは、費用対効果が低いといえるでしょう。
■低温やけどを負ってしまうおそれがある■
ホットカーペットの使い方を誤ると、低温やけどのリスクが高まります。
低温やけどは、40〜50度ほどのものに長時間触れ続けることで起こるやけどです。
じんわりと暖め続けられるホットカーペットだからこそ、使い方に注意しなければ低温やけどによって皮膚を痛めるおそれがあります。
設定温度を高くしすぎないようにする、長時間同じ場所に当たり続けないよう姿勢を変えるなどの工夫が必要です。
ホットカーペットの電気代を節約する方法

ホットカーペットは使いたいけど電気代は節約したい、という場合は、以下の節約方法を実践してみてください。
断熱マットを活用する
ホットカーペットの下に断熱マットを敷くことで節電できます。
床の冷気を遮断することで、ホットカーペットが効率的に暖かくなるため、無駄な消費電力を抑えることが可能です。
設定温度を見直す
ホットカーペットの設定温度を見直すと、電気料金を抑えられます。
設定温度を高くすると電気代が高くなるため、できるだけ低い温度で使うのがおすすめです。
使わない時は電源を切る
ホットカーペットを使わないときは、電源を切るようにしてください。
電源を切れば無駄な電力を消費しないため、電気代を節約できます。
毛布を併用する
毛布を併用すると、ホットカーペットの暖かさを保ちながら節電できます。
毛布を併用することで熱を逃さないようにできるので、設定温度を低くしても暖かさを感じることが可能です。
他の暖房器具と併用する
ホットカーペットと他の暖房器具を併用することで、電気代を抑えられます。
エアコンや電気ストーブで部屋全体を暖めても、体が冷えている場合はなかなか暖まりません。
ホットカーペットで足元や体を暖めながら、エアコンや電気ストーブで部屋全体を暖かくすれば、無駄な電力消費を抑えながら快適性を保てます。
電力会社を切り替える
電気代が高いと感じるなら電力会社を切り替えるのもおすすめです。
電力会社はさまざまな電気料金プランを用意しているため、今よりも電気代がお得になるプランがないか探してみてください。
省エネ機能がついた製品に買い替える
すでにホットカーペットを使っている場合は、省エネ性能の高い製品に買い替えることで電気代を抑えられる可能性があります。
最新の製品のほうが省エネ性能は高く、使用時間が同じでも電気代が安くなる傾向があるので、買い替えを検討してみてください。
買い替えるのにおすすめなホットカーペット2選!

ホットカーペットの買い替えを検討しているなら、以下の2つの製品がおすすめです。
それぞれの特徴を確認しましょう。
SKJ(エスケイジャパン) SKJ-KS2J-G 2畳用

「SKJ-KS2J-G」は、 2畳用のホットカーペットです。
自動6時間切タイマーを搭載しており、電源を切り忘れることなく使用することができるため、節電にもつながります。
ダニを除去する機能も搭載されているので、衛生的に使えるのが魅力です。
TEKNOS TWM-1000M [ホットカーペット(1畳用・木目フローリングタイプ)]

「TEKNOS TWM-1000M」は、1畳用のホットカーペットです。
コンパクトなので少ない消費電力で稼働でき、電気代を安く抑えられます。
温度調節機能により、適温を保てるのがポイントです。
ダニ退治機能で清潔に使えるため、小さめのホットカーペットを探している方は購入を検討してみてください。
まとめ

ホットカーペットの電気代は1時間あたり6.2〜21.7円程度で、部屋全体を暖める暖房器具よりは安いものの、暖房効果を考えるとやや高めといえます。
そのため、設定温度の見直しや断熱シートの使用などの工夫をして、電気代を節約すると良いでしょう。
省エネ性能の高い製品に買い換えれば電気代を抑えられるので、おすすめ製品をチェックして購入を検討してみてください。