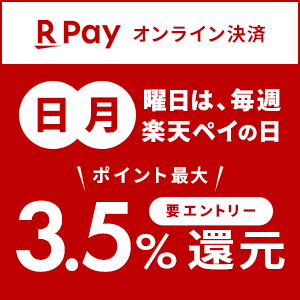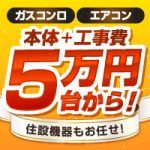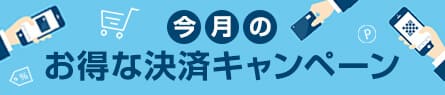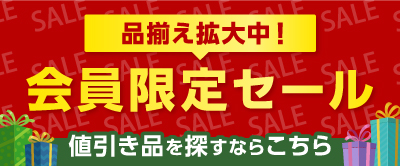湿度の高い時期が多い日本では、効率的に部屋の湿気を取り除ける除湿機が活躍します。
梅雨時に限らず除湿機を使う家庭も多いですが、そうなると気になるのが電気代です。
除湿機を使うときにかかる電気代がどのくらいかわかれば、節約が必要かどうかを判断できます。
今回は、除湿機の種類ごとの電気代について解説します。
電気代を節約しながら使う方法や製品の選び方のほか、おすすめ製品も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
除湿機の種類と電気代の目安

除湿機の電気代は、種類によって異なります。
除湿機はコンプレッサー方式、デシカント方式、ハイブリッド方式の3種類に分けられるため、それぞれの特徴と電気代を確認しましょう。
除湿機の電気代を算出するときは、以下の計算式を用います。
「消費電力(W)÷ 1,000 × 使用時間(h)× 電気料金単価(円/kWh)」
消費電力は、製品の取扱説明書やメーカーの公式サイトに記載されています。
電気料金単価は、契約している電力会社や電気料金プランによって変わるため、契約内容を確認してみましょう。
なお、本記事では電気料金単価を31円/kWhとして計算します。
これは、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が算出している単価です。
コンプレッサー方式
コンプレッサー方式の除湿機は、内部で空気を冷やして結露を発生させることで、室内の湿度を下げるのが特徴です。
消費電力が小さいため、電気代を節約できるというメリットがあります。
ただし、本体が大きくなりやすいので、置き場所や保管場所には注意が必要です。
また、低温では除湿能力が落ちるため、冬の使用は向きません。
他の方式と比べて運転音も大きくなりやすいので、使うタイミングには工夫が必要です。
コンプレッサー式の除湿機の消費電力は、120〜400W程度が一般的です。
先述の計算式に当てはめると、1時間あたりの電気代は3.72〜12.4円となります。
コンプレッサー方式 除湿機 はこちら
デシカント方式
デシカント方式の除湿機は、内部にヒーターが搭載されており、空気を温めて除湿をします。
空気を取り込んで温めるため、室温が上がるのが特徴です。
冬の結露対策や、洗濯物の部屋干し時の湿気対策に便利です。
また、ヒーターで空気を温める性質上、気温によって除湿量が左右されません。
いつでも高い除湿力を発揮するため、湿気を取り除けます。
コンパクトで軽量な製品が多く、運転音も小さいです。
ただし、除湿機能を発揮するためにヒーターを使うので、消費電力が大きく電気代は高くなりやすいのがデメリットです。
また、温かい空気が放出されて室温が上がるため、夏の使用には向きません。
デシカント式の除湿機の消費電力は、280〜500Wほどです。電気代は、1時間あたり8.68〜15.5円となります。
デシカント方式 除湿機 はこちら
ハイブリッド方式
ハイブリッド方式の除湿機は、コンプレッサー方式とデシカント方式の機能を組み合わせた製品です。
部屋の温度や湿度に応じてコンプレッサー式とデシカント式の比率を調整するため、1年中快適に使えます。
それぞれのデメリットを補えるので、通年使える除湿機を探している方におすすめです。
ただし、2つの方式を採用していることから、製品サイズは大きくなりやすく、小型の除湿機を探している方には向きません。
価格も高くなりやすいので、予算内に収まるかどうかを考える必要があります。
ハイブリッド式の除湿機の消費電力は、280〜600W程度が多いです。
電気代は、1時間あたり8.68〜18.6円となります。
ハイブリッド式 除湿機 はこちら
電気代を節約しつつ効果的に除湿機を使う方法

除湿機の電気代は1時間あたり3.72〜18.6円と、製品によって大きく差があることがわかりました。
自宅で使っている除湿機の電気代が気になるものの、湿度の高い季節や部屋干しした衣類を乾燥させたいときには、除湿機が便利です。
そこで、電気代を節約しつつ効果的に除湿機を使う方法を実践するのがおすすめです。
具体的な方法を、以下で紹介します。
扇風機やサーキュレーターと併用する
除湿機は、扇風機やサーキュレーターと併用することで除湿機能が高まり、電気代を節約することが可能です。
除湿機で部屋の湿気を取り除こうとすると、ある程度の時間が必要です。
サーキュレーターや扇風機は、風を送って室内の空気を循環させる役割を果たします。
そのため、部屋全体の湿度を効率的に下げることが可能です。
扇風機やサーキュレーターは、衣類乾燥時に使うと洗濯物の乾きを早めるというメリットもあります。
定期的にメンテナンスを行う
除湿機にかかる電気代を抑えたいなら、定期的にメンテナンスを行いましょう。
除湿機を効率的に稼働させるためには、溜まった汚れを取り除く必要があります。
フィルターやタンクなどにゴミやカビなどが付着すると、稼働効率が低下して電気代が多くかかってしまいます。
フィルターのゴミを掃除機や水洗いで取り除いたり、使用後にタンクを乾燥させたりしてこまめに手入れをしてください。
運転モードを切り替える
除湿機の電気代の高さが気になるなら、運転モードを切り替えるのも節約方法のひとつです。
製品によっては、弱・中・強やエコモードなど複数の運転モードが用意されています。
基本的に控えめな運転であるほど電気代を抑えられるため、弱モードやエコモードなどを利用するのがおすすめです。
ただし、湿度が非常に高い梅雨時などは、弱モードやエコモードでは快適性が損なわれるケースがあります。
臨機応変に運転モードを変え、電気代の削減と快適性を両立できるようにしましょう。
洗濯物の干し方を見直す
洗濯物を室内干しした結果湿度が上がるのを避けるために除湿機を使う場合は、干し方を見直すことで電気代を節約できる可能性があります。
洗濯物同士の距離が近い状態で干してしまうと、乾きにくくなっていつまでも湿度が下がらない状態が続きます。
洗濯物の間に拳1個分ほどの空間をあければ、乾きやすくなるため除湿機を稼働させる時間を短くすることが可能です。
省エネモデルに買い替える
除湿機を購入してから長い年数が経過しているのであれば、省エネモデルに買い替えることで節約できる可能性が高まります。
家電は、最新モデルほど省エネ性能が高いので、近年発売された製品を購入すれば電気代が安くなる傾向があります。
省エネにつながる機能を搭載しているか、消費電力が抑えられるかなどを確認したうえで買い替えるといいでしょう。
除湿機の選び方

これから除湿機を購入する方や買い替えを検討している方は、
選び方のポイントを抑えることで電気代の節約や快適性の向上につなげられる可能性があります。
以下で具体的な選び方を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
除湿方法で選ぶ
除湿機の除湿方法は、コンプレッサー式とデシカント式、ハイブリッド式の3種類です。
どの方式を選ぶべきかは、希望や使用環境によって異なります。
電気代を安く抑えたいのであれば、コンプレッサー方式の除湿機を選ぶといいでしょう。
ただし、低温で使う場合は十分な除湿効果を得られないことがあるため注意が必要です。
コンパクトで軽く、温度にかかわらず使える除湿機が欲しいならデシカント方式がおすすめですが、電気代は高くなります。
1年中使えて効率的に除湿したいなら、ハイブリッド方式が適しています。
サイズが大きく価格も高めなので、予算内に収まるかどうかを考えて選びましょう。
除湿できる水分量で選ぶ
除湿機は、除湿できる水分量で選ぶことも大切です。
製品ごとに使用環境として適切な部屋の広さが示されているため、確認したうえで選びましょう。
また、タンク容量も確認すべきポイントです。
タンク容量が小さければすぐ満水になって水を捨てる手間がかかるので、3L以上の容量があるものを選んでみてください。
機能性で選ぶ
製品によっては除湿以外の機能が搭載されているものもあるため、機能性で除湿機を選んでもいいでしょう。
例えば、空気清浄機能が搭載されている除湿機であれば、部屋の空気を綺麗に保てます。
衣類乾燥機能やカビ防止機能、自動停止機能などが付いている製品もあるので、確認してみてください。
省エネ機能のついた除湿機3選!

省エネ性能の高い除湿機を購入しようと考えているなら、以下の3つの製品がおすすめです。
それぞれの特徴を確認し、興味を持てたものを選んでみてください。
SHARP CV-R71-W ホワイト系

「SHARP CV-R71」は、コンプレッサー方式の除湿機です。
梅雨時や夏の室内干しに高い効果を発揮し、速やかに湿気を取り除きます。
プラズマクラスター搭載で、生乾き臭などを消臭できるのも嬉しいポイント。
洗いにくい衣類の消臭も実現します。
ホースをつなぐことで連続排水ができるため、水を捨てる手間を省くことが可能です。
SHARP CV-RH140-W ホワイト系

「SHARP CV-RH140-W 」は、ハイブリッド方式の除湿機で、1年中安定した除湿能力を発揮します。
上下にも左右にも乾いた風を届けられるため、衣類を速やかに乾かすことが可能です。
プラズマクラスターにより、消臭や除菌もできます。
SHARP KI-RD50-W ホワイト系

「SHARP KI-RD50 」は、除湿機と加湿器、空気清浄機の機能を併せ持っています。
衣類乾燥や除湿ができるだけでなく、乾燥が気になる季節には加湿も可能。
プラズマクラスターによって空気清浄もできるので、年中さまざまな目的で活用できます。
多機能な製品としてはスリムな設計で、置き場所に困りにくいのもポイントです。
除湿機の電気代を把握して、節約方法を実践しよう

除湿機の電気代は、1時間あたり3.72〜18.6円と幅が広いです。
除湿方法によって異なるため、購入する際は方式ごとの電気代や特徴を考慮したうえで製品を選びましょう。
除湿できる水分量や機能などにも注目して選べば、快適に除湿機を使えます。
電気代を抑える工夫をしながら除湿機を使って、部屋の湿度を適切に保ちましょう。